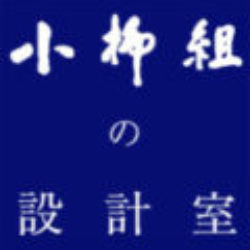日本の伝統建築や明治大正時代の洋風・擬洋風建築などは、建築関係以外の人にとっても、肌感覚としてその美しさや価値を自然に理解できる。
そのため歴史的遺産として保存すべきという意見も通りやすい。
実際、文化財への登録やヘリテージマネージャーという専門家らの活動によっても守られてきている。
一方、昭和以降の近代建築、主に鉄骨やコンクリートでできたいわゆるモダン・ムーブメントの時代の建築は、来歴や価値を顧みられることなく老朽化や経済効率を理由にいとも簡単に姿を消してしまうものも少なくない。
伝統建築のような解りやすさがないものも多いので、DOCOMOMOという組織がこの時代の建築の再評価と保存啓発に取り組んでいる。
現在国内では、280棟あまりがその価値を見出されて登録済であり、毎年その数を増やしている。
新潟県内での登録は、
新潟市体育館 [宮川英二+加藤渉(構造)] 1961年、
糸魚川善導寺 [渡邉洋治] 1961年、
長岡市立互尊文庫 [吉武泰水他(日本図書館協会施設委員会)] 1967年
の3件である。
ところで、加茂市に現存するこの時代の建築。
私が勝手に登録推薦するとしたら、この2つかな。
加茂市民体育館 [棚橋諒(担当:川崎清)] 1964年
天神林浄水場 [ ] 1973年
できるなら、メンテナンスや改修を図りながらずっと使い続けられると良いのだが、、、。


PS. 上記 天神林浄水場の設計者をご存知の方、ご教授を!