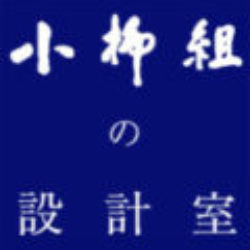佐渡金山が世界遺産登録されたとか、、、。
石見銀山や軍艦島などもそうだけれど、産業遺産と呼ばれるカテゴリーのものは、単純に「美しさ」とか「楽しさ」とかのドキドキ感が欠落しているように思う。
観光資源として考えるならば、もう一度訪れたいと思わせる直感的な美しさが必要だし、あそこはいいよと自信を持って人に勧めたくなる感動的なシーンを見せてほしいのだ。
関連する北沢選鉱場の遺構を美術館にコンバージョンするとか、相川の街中を小判作りの現場を再現したテーマパークにするとか、簡単ではないけれどそれくらいのエネルギーを投入して必見ポイントとしての価値を高めていってほしい。
もっとも、金山関連だけではリピーターの獲得は難しい。
佐渡全体のあらゆる素材を総動員して、一泊じゃとても回りきれない感を出していかないと。宿根木が吉永小百合のCMで一躍脚光を浴びたように、磨けば光る石がたくさんあるのだから。
要は磨き方次第。
例えば、能や太鼓や人形浄瑠璃などの伝統芸能。
開催日時が限られていて見たいと思っても日程が合わないことが多い。
海外リゾートがやっているようにホテルの庭とか、常設の観光劇場とかで連日日替わりで楽しめると良いのにと思う。
それから、島内の見どころが散在している佐渡では移動がレンタカー頼みになりがち。
休日くらいは車を運転したくないと思う私は、ホテルなどのオプショナルツアーのメニューをもっと充実させてほしい。
特に酒蔵見学で試飲を楽しんだり、昼食に牡蠣小屋で一杯とか。
ゆったりとした大人の休日を満喫できる選択肢が豊富にあること、それが観光地として長く愛され続けるための生命線である。